海外からも注目され、日本文化の一翼を担っている和菓子。
見た目や味の繊細さに魅了され、和菓子が好きという和菓子ファンは意外と多いものです。
一方で、和菓子店には「売上が伸びない」といった声が目立ち、廃業に追い込まれる中小企業が増えています。
和菓子は祭事などの季節柄の需要や贈答品としての需要など、底堅い需要があるのに、
一体なぜ多くの和菓子店が苦しい経営に迫られているのでしょうか。
今回は、「和菓子業界が抱える課題」を整理しつつ、
買い手の笑顔と作り手のやりがいが感じられる
明るい未来が描ける和菓子店経営について、私なりに考えてみました。
よろしければ最後までお付き合いください。
和菓子業界が抱える課題とは
まず、私が考える和菓子業界の課題は大きくこの3つ
- 伝統文化の衰退
- 消費者の減少
- 若者の職人離れ・後継者不足
この傾向は地方に行くと特に顕著で、和菓子店減少の要因となっているように感じます。
今、和菓子店経営に必要なこと
ブランディングを経営の柱に
美味しくて手軽に手に入るコンビニスイーツが台頭し、和菓子店は苦戦を強いられています。
最近はコンビニのスイーツ部門もすごく研究されていて、質の高いものが多く売られています。
美味しさや価格でコンビニに張り合おうとしても、勝ち目はないと感じます。
それならば、コンビニが持っていないもの、それを独自性として経営の柱におき、お客さんや社員の共感を得たらどうでしょうか。
例えば、作り手の思いをストーリーにしたり、歴史や素材のこだわりをブランド力にするといったように。
ブランド力を高めると次のような効果が期待できます。
- お客さんのリピート率向上
- SNSなどでの認知度向上
- 価格競争に陥らない
- 社員のモチベーション向上
価格と価値のミスマッチを減らす
一般的に、和菓子の価格は少し高めだと思いませんか?
それは、原材料費の価格のほか、製造工程の作業の多さが影響しています。
手間ひまかけて製造してるのに、価格設定を安価にしないと売れない。
そんな悪循環に陥っているケースがあります。
生産コストに見合った価格設定をすべきところですが、ただ値上げをすればよいということではありません。
ブランディングをしっかり行ったうえで、その価値を伝え、正当な価格を設定する必要があります。
技術継承とイノベーションの両立
日本文化の一翼を担う和菓子は、技術の継承が欠かせません。
しかし昔からの味を引き継ぐだけでは、新規顧客の開拓にはつながりません。
特に若い人を取り込むには、イノベーションが必要です。
- 新しい素材や異文化との融合
- デザインの革新
- 若手スタッフの提案の活用
- 和菓子教室やワークショップなど体験価値の提供
根底にある歴史や文化を守りながらも、変化を受け入れていく柔軟性が必要です。
和菓子職人の育成
和菓子職人の仕事環境は、過酷を極めるうえ、まだまだ職人世界特有の「見て覚えろ」「叱られて学べ」といった風習が色濃く残っています。
長時間労働、低賃金、過酷な肉体労働といった環境では、新人が「これ本当にやっていけるのかな・・・」と不安になるのはしかたありません。
- 労働対価に応じた休暇制度
- 勤務時間の明確化
- 技術習得のロードマップ化
- マニュアル・指導体制の整備
- 作業環境の改善
これからの時代、「修行」ではなく、しっかりとした「キャリア」として和菓子職人の道が描けるようにすることが必要です。
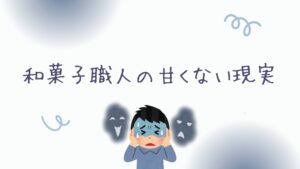
まとめ
和菓子は機械で製造したものよりも、日持ちのための添加物を配合したものよりも、やっぱりシンプルな素材で手作りしたものが一番美味しいと感じます。
コンビニスイーツの台頭や材料費の高騰に押され、個人の和菓子店は苦しい経営を強いられていますが、個人的には和菓子産業には伸びしろが大いにあると期待しているのです。
最後までお読みいただきありがとうございました。
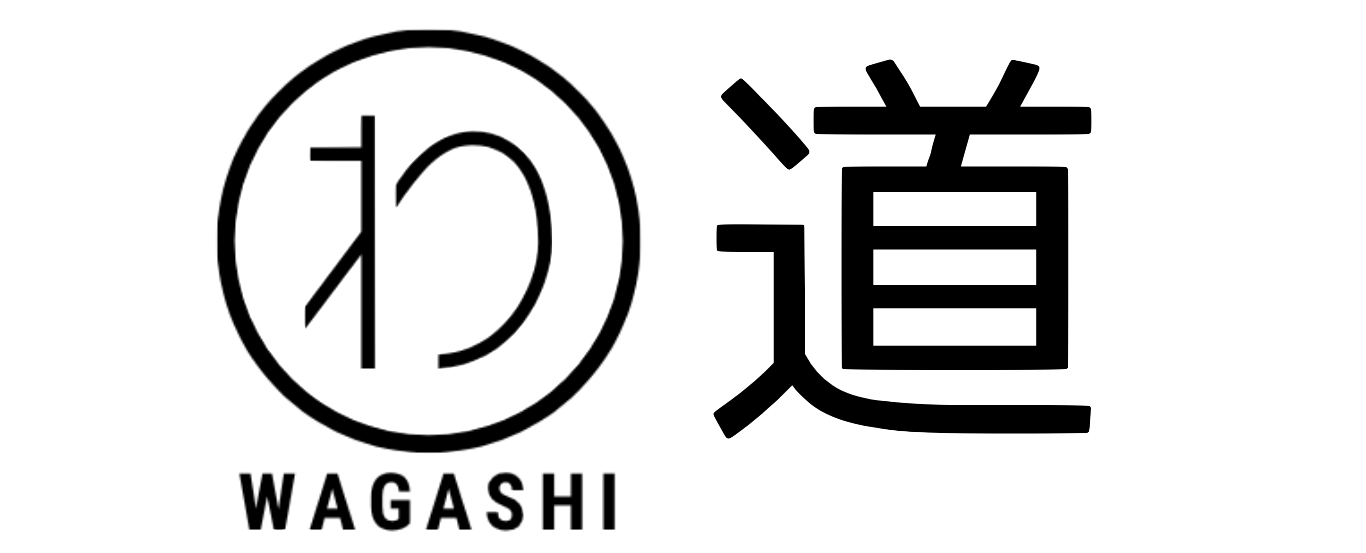
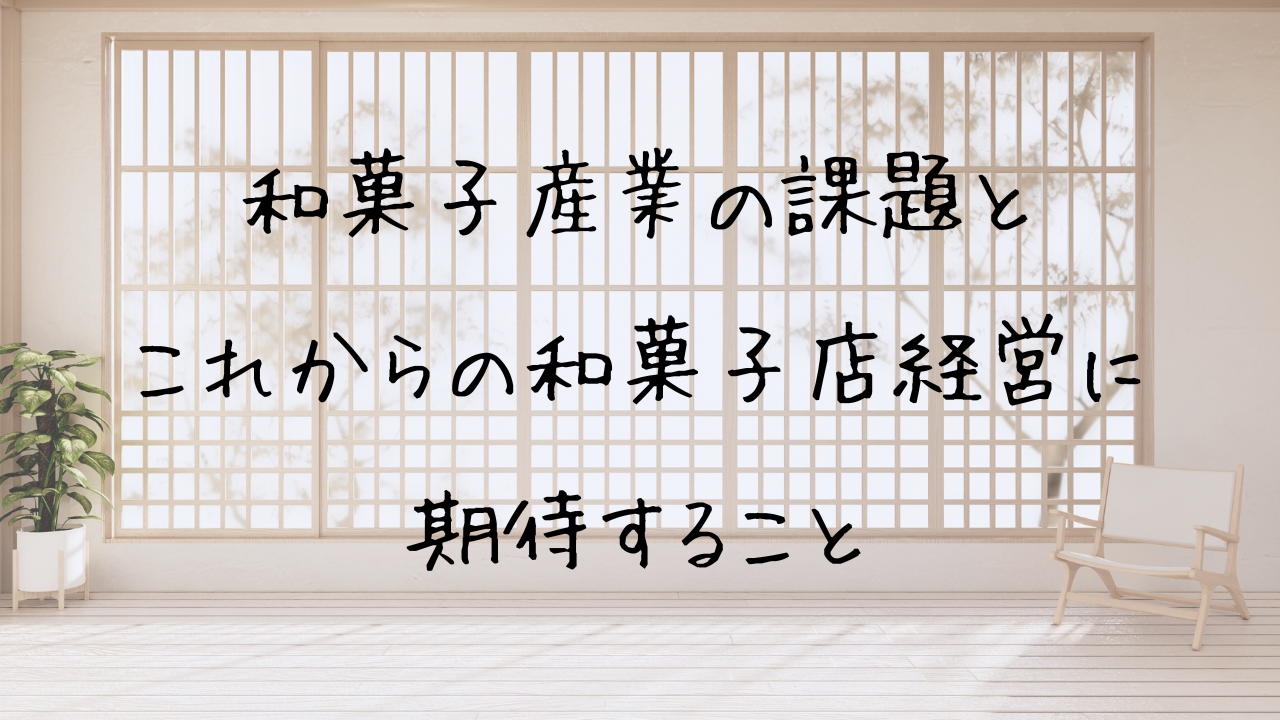
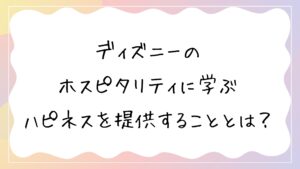
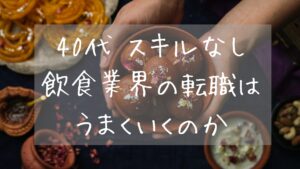
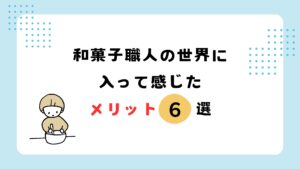
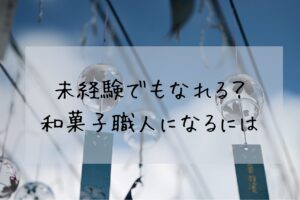
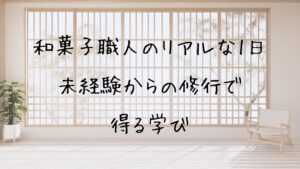
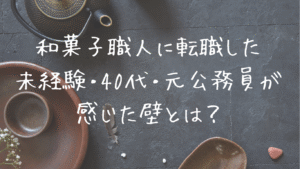
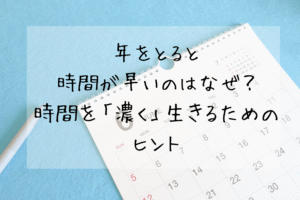
コメント