四季折々の食材、栄養バランスの良さなどから近年注目を集める和食文化。
その一つである和菓子は近年人気が高まっています。
前回の記事では、「和菓子職人になりたい」という方に向けて、和菓子職人のメリットを紹介しました。
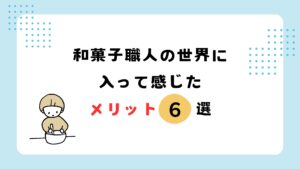
一方、和菓子職人の仕事はよい面ばかりではありません。
和菓子の製造現場は、想像よりずっと厳しい世界
そこで今回は、和菓子職人の「甘くない現実」をいくつか紹介します。
和菓子職人の「甘くない現実」
年齢、学歴よりモノを言うのは“キャリア”
和菓子の世界では、年齢や学歴よりも「どれだけやってきたか」が大事。
現場での経験、センス、技術がモノを言う世界だからです。
年上でも経験が浅ければ下っ端。
逆に若くても、キャリアが長ければ職人として一目置かれます。
厳しい上下関係 パワハラ横行
これは、和菓子に限らず、職人気質の現場にはよくあることのようです。
複数の和菓子製造の現場を経験した同僚に聞くと、「言葉の暴力」や「精神的プレッシャー」が常態化しているところは多いそうです。
年末年始、年中行事は休めない
土日祝日はもちろん、年末年始などみんなが休んでいる時こそ繁忙期。
また、正月、節句、お盆、お彼岸、七五三など年中行事の時もフル稼働になります。
世間が休んでいる時は自分も休みたくなりますが、こうした需要が和菓子産業の下支えとなっているので割り切って働いてます。
夏は売上が落ちる
夏は、和菓子需要が減退します。
餅菓子や焼き菓子の代わりに、寒天や葛を使った菓子を出しますが、それも売れ行きに限界があります。
この時期は製造が減るので、厨房の大掃除がはかどります。
立ちっぱなし、力仕事多めの体力勝負
餡を炊く、もちをつく、大量の材料を運ぶなど、和菓子職人の仕事は想像以上に重労働。
慢性的に手首や腕が腱鞘炎状態です。
しかも厨房は、夏はとにかく暑い。そして冬は水が冷たい。
労働環境は過酷そのものです。
辞めていく人が多い
長時間・低賃金・指導の厳しさで若手が定着しない傾向にあります。
技術習得前に心身が壊れるケースも。
老舗が多く、伝統を重んじる
長時間労働、厳しい上下関係、薄給。続けるのが難しい環境が揃っているため、残っている人の多くは家業を継ぐケース
老舗では親から子へ継がせる“血筋”が重視されます。
だからレシピも工程も、簡単には変えられません。
イノベーションが受け入れられづらく、昔からの伝統を引き継ぐことが尊ばれます。
給料が少ない
“和菓子=高級品”というイメージがあるかもしれませんが、作るのに手間がかかる分、利益率が低いので給料に還元されにくいです。
原材料費や光熱費が上がっているのに、そうそう値上げもできず困っている店も多いです。
ビジネスとしての魅力が乏しいため、新規参入も多くありません。
それでも和菓子業界を支える職人がいる
ここまで読むと、和菓子職人になることを諦めたくなるかもしれません。
でも、この世界に残る人たちは本当に和菓子が好きなんです。
味や見た目だけではない、和菓子が織りなす季節感や伝統を守る誇り。
食べて喜んでもらえるやりがい。
厳しく辛い現実があっても、手を動かし続ける職人たちの想いが、今の和菓子業界を支えているのです。
和菓子職人の世界のこれから
ここで挙げた一面は、全ての和菓子屋に共通するものではありません。
しかし確実に言えることは、今、和菓子職人の世界は、「職人離れ・後継者不足・低収益・保守的な体質」といった深刻な課題を抱えています。
若者が「やってみたい」と思える。
家族に「誇れる仕事だ」と思ってもらえる。
そんな仕事のひとつになればいいなと思います。
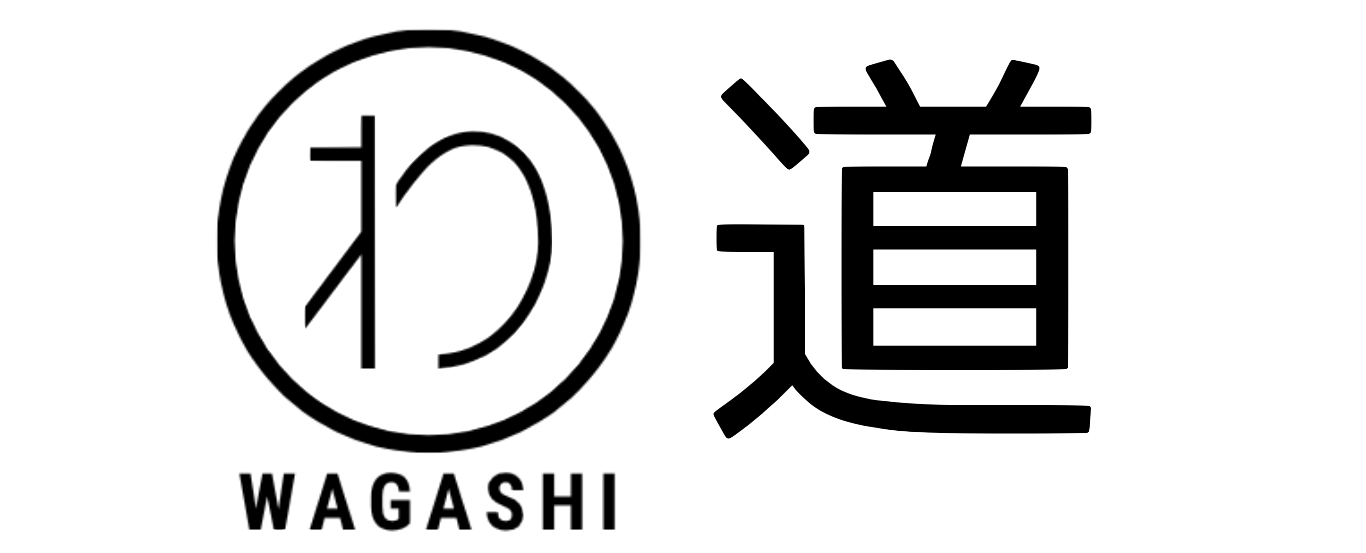
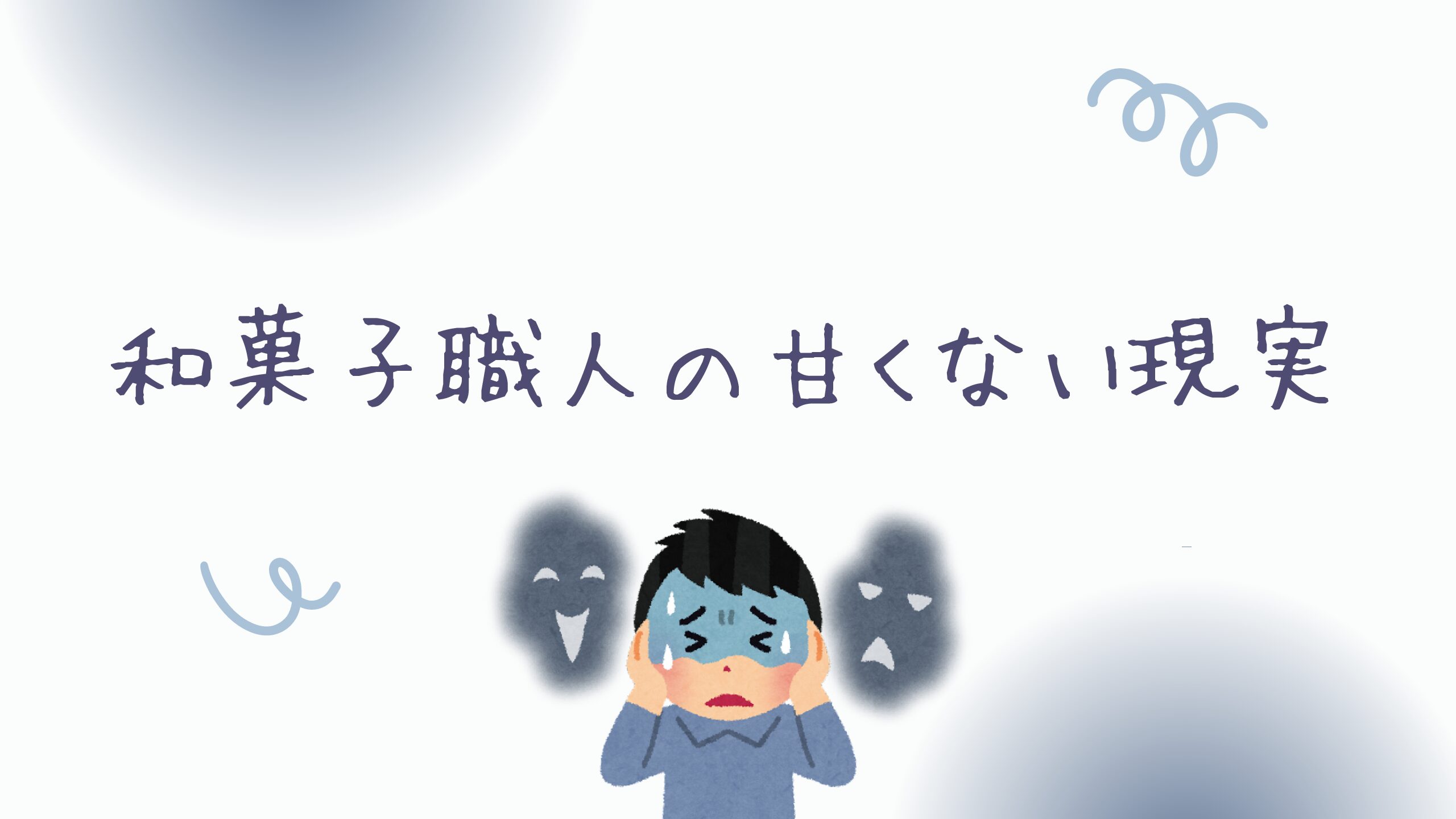
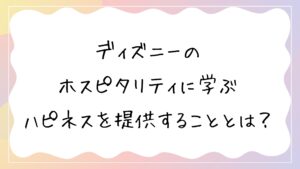
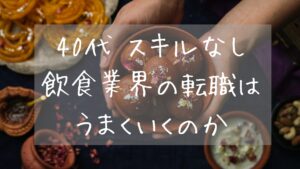
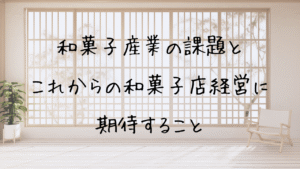
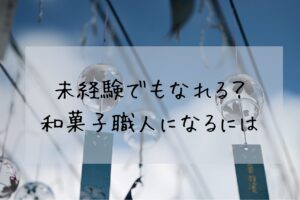
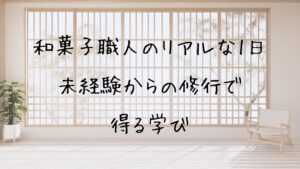
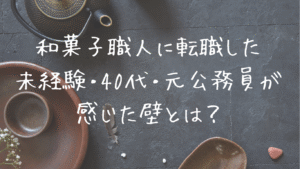
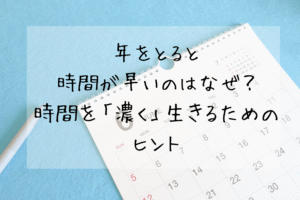
コメント